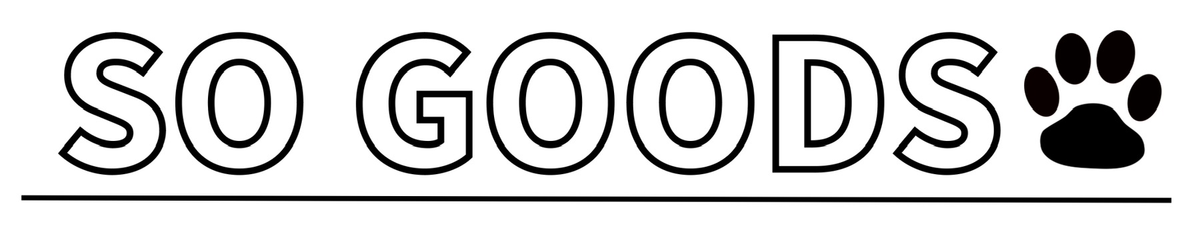愛犬の吠える問題を解決!原因と対策、しつけ方法を徹底解説

「愛犬の無駄吠え止まない…」「近所迷惑になっていないか心配…」と悩んでいませんか?
犬の無駄吠えは飼い主にとってストレスとなるだけでなく、近隣トラブルにも発展しかねない深刻な問題です。この記事では、犬が吠える様々な原因と、原因に合わせた効果的な対策、具体的なしつけ方法を解説します。
吠え癖対策グッズの選び方やおすすめ商品も紹介!
この記事を読めば、愛犬の無駄吠えを減らし、愛犬との穏やかで幸せな暮らしを実現できるでしょう。
犬が吠える原因を特定しよう

愛犬が吠えるのには様々な理由があります。吠えの種類や状況を把握し適切な対策を講じることが大切。
まずは愛犬がなぜ吠えているのか、その原因を探ることから始めましょう。
要求吠え
欲求不満が原因で吠える
遊んで欲しい、お腹が空いた、退屈しているなど、欲求が満たされない時に吠えることがあります。欲求不満が原因の吠えは、その欲求を満たしてあげることで解決できる場合が多いですが、常に要求に応じていると、吠えれば要求が通ると学習してしまいます。適切なしつけと、欲求を満たすバランスが重要です。
飼い主の気を引きたくて吠える
飼い主にかまって欲しいという欲求から吠えるのも要求吠えです。吠えることで飼い主の気を引こうとします。この場合、吠えている間は無視し吠え止んで静かになったら褒めてあげることを徹底しましょう。吠えなくてもかまってもらえると学習させることが重要です。
警戒吠え
知らない人や犬への警戒心から吠える
散歩中や来客時などに、知らない人や犬に対して吠えることがあります。これは、縄張りを守ろうとする本能的な行動と恐怖心によるものです。社会化トレーニング不足が主な原因です。
家のチャイムや物音に反応して吠える
チャイムの音や玄関の開閉音、外の物音などに反応して吠える犬もいます。外部からの刺激に対して警戒しているためです。徐々に音に慣れさせるトレーニングを行うことで、吠えを軽減することができます。
恐怖吠え
雷や花火などの大きな音に怯えて吠える
雷や花火などの大きな音に恐怖を感じて吠える犬は少なくありません。大きな音に慣れさせるトレーニングや、安心できる場所を提供することで、恐怖心を軽減することができます。
動物病院など苦手な場所での恐怖から吠える
動物病院など、苦手な場所での恐怖から吠えることもあります。過去の経験から恐怖心が生まれている場合は、少しずつ慣れさせるトレーニングが必要になります。
分離不安による吠え
飼い主と離れることへの不安から吠える
飼い主と離れることに強い不安を感じて吠える犬もいます。これは、飼い主への依存心が強いことが原因と考えられます。留守番に慣れさせるトレーニングが有効です。
留守番中に吠え続ける
飼い主がいない留守番中の間吠え続けるのは、分離不安の症状の一つです。近所迷惑になる可能性もあるため、早めの対策が必要です。
縄張り意識による吠え
自分の縄張りだと認識している場所に、他の犬や人が侵入してきた際に吠えることです。家の前を通る人に吠えたりするのも、縄張り意識によるものです。
自分の縄張りを守るために吠える
犬は本能的に自分の縄張りを守ろうとします。他の犬や人に対して吠えるのは、縄張りを守るための警告です。過剰な縄張り意識は問題行動につながる可能性があります。
他の犬や人に対して吠える
散歩中や自宅の庭などで、他の犬や人に対して吠えることがあります。これは、縄張り意識の表れです。適切なしつけでコントロールすることが重要です。
病気や痛みによる吠え
病気やケガによる痛みや不快感を訴えるために吠えることがあります。いつもと違う吠え方をする場合は、病気やケガの可能性も考え、動物病院を受診しましょう。
犬は言葉で伝えることができないため、吠えることで体の不調を訴えることがあります。いつもと違う吠え方や、元気がないなどの症状が見られる場合は注意が必要です。
痛みや不調の時は吠え以外にも、食欲不振、嘔吐、下痢、発熱など、病気やケガのサインを見逃さないようにすることが大切です。少しでも異変を感じたら、獣医師に相談しましょう。

犬の吠える対策 しつけ方法

愛犬の無駄吠えの種類に応じた具体的な対策と効果的なしつけ方法を解説します。吠えの根本原因にアプローチすることで、愛犬とのより良い関係を築き、快適な生活環境を実現しましょう。
要求吠えへの対策
要求に応じない
吠えているときに要求に応じると、吠えることで要求が通ると学習してしまいます。吠えている間は無視し、落ち着いてから要求に応じましょう。
吠えるのをやめたらご褒美をあげる
吠え止んだらご褒美をあげることで、静かにしていると良いことがあると学習します。おやつや褒め言葉などで正の強化を行いましょう。
アイコンタクトの練習
アイコンタクトは、飼い主とのコミュニケーションを深め、犬の要求をコントロールするのに役立ちます。アイコンタクトができたら褒めてあげましょう。
警戒吠えへの対策
社会化トレーニング
子犬の時期に様々な環境や人や犬に慣れさせることで、社会性を身につけ警戒心を軽減することができます。成犬になってからも、少しずつ新しい経験をさせていきましょう。
系統的脱感作トレーニング
警戒する対象に徐々に慣れさせるトレーニングです。最初は遠くから見せ、徐々に距離を縮めていくことで、恐怖心を克服させます。焦らずゆっくりと進めることが重要です。
安心できる環境を作る
犬が安心して過ごせる場所を用意し、安心できるおもちゃやブランケットなどを置いて落ち着けるようにします。静かな環境を保つことも重要です。
恐怖吠えへの対策
安心できる場所を提供する
クレートやケージなどを利用し愛犬の安心できる空間を作ってあげます。犬が恐怖を感じたときに逃げ込める安全な場所を用意しましょう。
大きな音に慣れさせる
雷や花火の音に慣れさせるためには、録音した音を小さい音量から徐々に聞かせ慣れさせていく方法があります。無理強いせず、犬の様子を見ながら進めましょう。
獣医師に相談する
恐怖吠えがひどい場合は、獣医師に相談し抗不安薬などの処方を検討することもできます。自己判断せず、専門家のアドバイスを受けることも大切です。
分離不安への対策
留守番に慣れさせる練習
最初は短時間から始め、徐々に時間を延ばしていくことで留守番に慣れさせます。留守番中は、おやつやおもちゃを与えて気を紛らわせるのも効果的です。
クレートトレーニング
クレートを犬にとって安心できる場所にすることで、留守番中の不安を軽減することができます。クレートトレーニングは、犬の安全を守る上でも重要です。

安心できるおもちゃやグッズを用意する
留守番中に犬が寂しがらないように、お気に入りのおもちゃや飼い主の匂いがついたタオルなどを用意しておきましょう。知能玩具なども効果的です。
投薬治療を併用する
分離不安によって無駄吠え以外にも、よだれや激しい呼吸(パンティング)、自傷行為(皮膚の舐めこわし)など、過度の症状がいられる場合は、トレーニングと一緒に抗不安薬の投与を併用していくことも検討しましょう。
獣医師に相談し、指示に従い投与します。
縄張り意識による吠えへの対策
縄張りを意識させない環境づくり
窓際に犬を近づけないようにしたり、カーテンを閉めることで、外からの刺激を減らし吠える機会を減らします。
他の犬との適切な接し方を学ぶ
他の犬と適切に接することで、社会性を身につけ縄張り意識を弱めることができます。ドッグトレーナーの指導を受けるのも効果的です。

吠え癖対策グッズ
愛犬の無駄吠えにはさまざまな対策グッズが販売されています。
犬への負担を最小限にするためにも、トレーニングと併せて補助的に使用しましょう。
警告音式
犬が吠えるとビープ音(警告音)を発し、不快感を与えることで吠えを抑制します。ビープ音と一緒に振動するものを多く発売されています。
音量レベルを調整できるものがおすすめです。
振動式
犬が吠えると振動を与え、吠えを抑制します。振動の強さを調整できる製品もあります。振動に敏感な犬には注意が必要です。
スプレー式
犬が吠えた時に。無臭の噴射剤やラベンダーなどが配合されたスプレーを噴射し、吠えを抑制します。
噴射音で吠える行為を抑制する物もあります。使用の際は、1m以上距離をとって顔に噴きかけないように使用します。
噴射剤にアレルギーのある犬には使用できません。
超音波発生装置
犬が吠えると超音波を発し、吠えを抑制します。首輪型とは異なり、犬に装着する必要がありません。
設置場所や犬との距離によって効果が変わる場合があります。
リモコントレーニング
リモコン操作で、音や振動、電気などで犬に指示を出せるトレーニンググッズです。無駄吠えだけでなく、様々なトレーニングに活用できます。電気を使用する場合は、必ずレベルを最弱から設定し、刺激が強すぎる場合は使用を中止しましょう。
適切な使い方でトレーニングに用いる必要があります。
無駄吠え防止グッズは、あくまで補助的なツールです。使用にあたっては必ず取扱説明書をよく読み、正しく使用してください。根本的な解決のためには、吠える原因を理解し適切なしつけを行うことが重要です。
問題が深刻な場合は、ドッグトレーナーや獣医師に相談することをおすすめします。

犬が吠える問題に関するQ&A
愛犬の吠え声にお困りの飼い主さんのよくある質問とその回答をまとめました。
子犬の無駄吠え対策はどうすれば良いですか?
子犬の無駄吠えは、社会化期における重要な課題です。この時期に適切な対処をしないと、吠え癖が定着してしまう可能性があります。
まずは、子犬の社会化を積極的に行い色々な刺激に慣れさせましょう。クレートトレーニングも一緒に行うと効果的です。クレートを安心できる場所として認識させることで、無駄吠えを軽減できます。要求吠えの場合は、要求に応じず無視することが大切です。吠えるのをやめたら褒めて良い行動を強化しましょう。
老犬の吠え癖はどうすれば治りますか?
老犬の吠え癖は、認知症や加齢による不安などが原因であることもあります。急に吠え始めた場合は、まずは動物病院で診察を受け病気の有無を確認しましょう。病気ではない場合は、生活環境を整え、安心できる空間を作ってあげることが重要です。昼夜逆転している場合は、生活リズムを整えることで改善されることもあります。
サプリメントの利用も検討してみましょう。
犬猫健康補助食品であるジルケーンなどは、犬の不安を軽減する効果が期待できます。動物病院専売サプリメントなので、獣医師に相談しながら適切な対応を行いましょう。
集合住宅で犬が吠える場合の注意点は何ですか?
集合住宅では、近隣への騒音に特に配慮が必要です。無駄吠え防止グッズの利用し吠えを抑制しながら、壁や床に防音対策を施しましょう。
日頃からしつけをしっかり行い、吠える原因の特定と適切な対策が重要です。近隣住民への配慮を忘れず、トラブルを未然に防ぎましょう。
日頃から近隣住民との良好な関係を築くことも大切です。挨拶を交わしたり、犬の吠え声について相談したりすることで、相互理解を深めトラブルを回避することに繋がります。
まとめ
愛犬の吠え声にお困りの飼い主さんへ、吠える原因と対策、しつけ方法を解説しました。犬が吠える背景には、要求吠え、警戒吠え、恐怖吠え、分離不安、縄張り意識、病気や痛みなど様々な原因が考えられます。それぞれの原因に合わせた適切な対策とトレーニングを行うことが重要です。
吠え癖を改善し、愛犬とのより良い共生を目指しましょう。